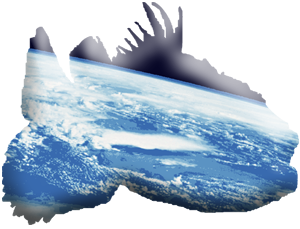(2018年2月22日追記)洗足論叢第46号にて、「ヴォーン・ウィリアムズ《チューバ協奏曲》のための研究ガイド」として以下の記事をアップデートしたものを掲載いただきました。リンク先からPDFをダウンロードできますので、そちらをお勧めします。こちらのページはその小論でも参考文献として扱っていますので、このまま残しておきます。
ヴォーン・ウィリアムズのテューバ協奏曲~その成立と分析~
(この小論は随分と昔にレポート提出用にまとめたものを再編成したものです。細かい部分で随時訂正を行う可能性があることをご了解下さい。)
レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ略歴
テューバ Tubaが現在のようにオーケストラの中に定位置を得たのは音楽史的に比較的新しい時代で、テューバ以前に低音管楽器として用いられていたセルパン Serpent、オフィクレイド Ophicleideとそれらの派生楽器からテューバがその位置を完全に取って代わったのは、ベルリオーズ、ヴァーグナーを端とする19世紀ロマン派の時代以降と考えてよい。オーケストラの機能が当時の作曲家たちによって拡大され、その結果音量・音域共に彼等の要求に絶えうる楽器として発明されたのがテューバだったのである。しかしながら、テューバがその演奏の分野を独奏曲まで広げたのは更に遅く、第2次世界大戦以降までその登場を待たなければならなかった。楽器自体の性能、演奏者の能力、両者のレヴェルが当時の作曲家たちを触発しなかったということは一つの理由として考えられる。また、何処かユーモラスな感をもたらすこの楽器の持つ独特な音色と独奏曲という分野とを結びつかせることは容易でなかったのかもしれない。このような状況の中で、音楽史上最初に書かれたテューバとオーケストラのための協奏曲がレイフ・ヴォーン・ウィリアムズ Ralph Vaughan Williams (1872-1958)の《テューバ協奏曲》 Concerto for Bass Tuba であった。
レイフ・ヴォーン・ウィリアムズはグスタフ・ホルスト Gustav Holst (1874-1934)と共に、20世紀前半に「イギリス音楽のルネサンス」を築き上げたイギリス最大の作曲家である。王立音楽大学とケンブリッジ大学で学び、ベルリンに留学してブルッフ Max Bruch (1838-1920)に、パリではラヴェルに師事した。オルガン奏者、トロンボーン奏者としても活動していたこの修業期間中にイギリス民俗音楽を研究し、30歳頃から本格的作曲活動に入る。国民主義的作風から出発した彼は1934年のホルスト、エルガーの死後、イギリス音楽界の指導的作曲家として活躍し、晩年に近づくにつれて一層精力的な創作を行った。彼の音楽は9曲の交響曲(第2番《ロンドン》が有名)をはじめ、オペラ、協奏曲、室内楽曲、声楽曲など多岐に渡るが、その多様な音楽形式の根底には、常にイギリスの17-18世紀の音楽、伝統的な民謡や賛美歌の世界が存在する。エリザベス朝時代の旋法やイギリス東岸の民謡から影響を受けた親しみやすい旋法的な旋律が和声の流動的な運動と結びつき、ラヴェルを思わせる透明なオーケストレーションによって歌われるのが、彼の特徴といってよいだろう。彼の生涯において作曲された協奏曲、若しくは協奏曲的な作品(独奏楽器を伴うもの)は次の通りである。
| 作曲年 | 作品名及び編成 |
|---|---|
| 1902-4 | Fantasia for pianoforte and orchestra |
| 1914, rev. 1920 | The Lark Ascending, a Romance for violin and small orchestra |
| 1925 | Flos Campi for viola, wordless chorus, and orchestra |
| 1925 | Concerto in D minor for violin and strings “Concerto Accademico” |
| 1929 | Fantasia on Sussex folk tunes for cello and orchestra |
| 1926-1931 | Concerto in C major for piano |
| 1934 | Suite for viola and orchestra |
| 1944 | Concerto in A minor for oboe and strings |
| 1946 | Concerto in C major for 2 pianos |
| 1949 | Fantasia on Old 104th Psalm Tune for piano, chorus, and orchestra |
| 1951 | Romance in D flat for harmonica, strings and piano |
| 1954 | Concerto in F minor for Bass Tuba and orchestra |
以上のように、ピアノの為の曲が4曲、ヴァイオリン、ヴィオラ共に2曲、チェロ、オーボエ、ハーモニカ、テューバの為の曲が夫々1曲となっている。テューバと同じく、ハーモニカといった独奏楽器としては珍しい楽器を取り上げていることは注目すべき点であろう。また彼は後期の交響曲でウインド・マシーンやテューンド・ゴング、フリューゲルホルンと3本のサクソフォーン等を用いており、こういった新たな楽器の使用の可能性を用いて従来の管弦楽における音楽語法の拡大を考えていたことが推察される。加えて前述のように修業時代にトロンボーンを吹いていたことなどから、管楽器の扱いには書法的にも実際的にも通暁していたと考えられる。このことは《テューバ協奏曲》を作曲する上で大きな要素となったと考えらよう。
次に、《テューバ協奏曲》の初演時の状況について述べていこう。
《テューバ協奏曲》の初演とその周辺
| 原題 | Concerto in F minor for Bass Tuba and Orchestra |
|---|---|
| 作曲年 | 1954 |
| 楽器編成 | 独奏テューバ フルート2(2番はピッコロ兼) オーボエ クラリネット2 バスーン ホルン2 トランペット2 トロンボーン2 ティンパニ パーカッション2 (サイドドラム、トライアングル、バスドラム、シンバル) 弦5部 |
| 楽章構成 | I – Allegro Moderato (Prelude)II – Romanza (andante sostenuto)
III – Finale (rondo alla tedesca) |
| 演奏時間 | 13 minutes |
| 初演日時 | 1954年6月13日、ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールにおけるロンドン・シンフォニー・オーケストラのジュビリーコンサート |
| 初演者 | フィリップ・カテリネット独奏、サー・ジョン・バルビローリ指揮のロンドン・シンフォニー・オーケストラ |
| 献呈 | ロンドン・シンフォニー・オーケストラに。 |
初演当時のプログラム・ノートには作曲者自身の次のような言葉が掲載されている。
この協奏曲の形式はウィーン楽派(モーツァルトやベートーヴェン)のものよりも寧ろバッハのそれに近い。しかしながら、第1、第3楽章は両方とも手の込んだカデンツァで終わり、この点ではモーツァルトやベートーヴェンの形式と同様である。この音楽は全く単純で明白であり、(わざわざ)このような説明がなくとも聴くことが出来るであろう。楽器編成は木管楽器とホルン2、トランペット2、トロンボーン2、ティンパニ、パーカッション、そして弦楽器という所謂「シアター・オーケストラ」の編成で構成されている。(1)
作曲の動機は、前述のようにロンドン・シンフォニー・オーケストラによるジュビリーコンサートの作品委嘱を受けたことなのだが、何故その素材としてテューバの為の協奏曲を思い立ったのかは残念ながら明らかにはなっていない。当時の世評は余りよいものとはいえなかった。初演前、及び初演当時の2つの例を挙げよう。
初演前:
志の大きな演奏家にとってその将来は微かな希望を持てなくもないだろう。テューバによって表現されるべき才能たるものに、幾らかは働き口があるやも知れぬ。作曲家もこの楽器を熱心に研究し始め、自分達の才能を誇示する為の曲が作られるであろうか?そうすればテューバ奏者にも夜明けがやってくるかも知れぬ。ウィグモアー・ホールでのリサイタルやロイヤル・フェスティヴァル・ホールへの出演、アルバート・ホール、カーネギー・ホール、ワールドツアーも夢ではない???(2)
(“Tuba: Composers, Please note!”.Music, London, 1952.)
初演当時:
現在81歳であるヴォーン・ウィリアムズが、バステューバの為に協奏曲を書いた。この曲はレコード化されると同時に、来月フェスティヴァル・ホールで催されるLSO(ロンドン・シンフォニー・オーケストラ)の祝典コンサートでも演奏される。彼の前作であるハーモニカの協奏曲はラリー・アドラーのテクニックで辛うじて成功を収めた。今回ソロ・パートを務めるのはLSOの主席テューバ奏者フィリップ・カテリネットである。彼は肺活量の全部を使い切らなければならないだろう。通常テューバというものはトロンボーンのハーモニーの基礎を成すためのものだ。今回の20分間に及ぶ独奏はかなり手強い仕事となるであろう。(3)
しかしながら、初演後には幾らか好意的な批評も見られる。
…この曲については押し付けがましい所や、何かをもじったような所はない。テューバにステージの中央に立つまたと無いチャンスを与える為、作曲家はその表現力を研究するかなりの努力を惜しまなかった。…(中略)…決して代表作とはいえないが、恐らく代表作足りうる作品であろう。(4)
(Michael Kennedy, Liner notes for SJB102)
また、初演で独奏者の任を果たしたフィリップ・カテリネットと作曲者との初演前のリハーサルにおける記録は、次のようなものが残されている。
…作曲家は私が作品の解釈に対して余り気を使いすぎないようにと強調しました。
…フレージングやスラーの納まり方などについては、お互いに理解を得られました。
…初期のピアノ版では書かれていなかった第1楽章のカデンツァに現れる2つの短い高音域のフレーズは、結果として初演では省かれることとなったのです。
…(第3楽章において)初演後に作曲家はこの部分がジャーマンワルツであることと、レコーディングのときはより安定したテンポ間を強調することを指示してきたのです。(5)
(註)
- Kennedy, Michael. A Catalogue of the Works of Ralph Vaughan Williams. London: Oxford University Press, 1982. pp.229-300.
- Catelinet, Philip. “The Truth About the Vaughan Williams Tuba Concerto”. TUBA Journal, Greenboro: T.U.B.A., 1991. p.67.
- Ibid., pp. 68-69.
- Ibid., p. 71.
- Ibid., p. 69.
楽曲分析
分析にあたって、この曲のアーティキュレーションについての次のような記述に触れておきたい。
…不幸なことに、私は作曲者のピアノ・スケッチと(私が書き写した)このスコアを照らしあわす機会が無かったので、長年に渡っての紛糾の種を引き起こしてしまった。
(Roy Douglas, Working with Vaughan Williams – The Correspondence of Ralph Vaughan Williams and Roy Douglas. London: The British Library, 1988. p68. ISBN 0-7123-0148-8)
ここにあるように、現在出版されている譜面と自筆譜の間には、いくらかの相違がある可能性があるため、ここでの分析ではそのことについては特に触れないこととする。同様に、記譜音に関しては、現在出版されている譜面のものを分析の対象として取り扱うこととする。
では、各楽章ごとに分析を行うこととする。文中の練習番号1,2…はピアノ伴奏版(Vaughan Williams, Ralph. Concerto for Bass Tuba and Orchestra, Arrangement for tuba and piano. London: Oxford University Press. 1955. viii, 22p.)の練習番号を意味している。音名表記はドイツ音名による。
第1楽章 前奏曲(オーケストラ版のフルスコアにのみこの副題がみられる)アレグロ・モデラート(4分音符=96)へ短調 2/4拍子。
曲はオーケストラのトゥッティによる4小節の序奏で始まる。これは後に独奏部において展開される為、M1としておく。4小節目より始まるテューバの独奏は、へ音上のフリギア旋法のF-Ges-B-C-Esによる5音音階からなっている(=M2)。冒頭から練習番号1まではこのM2による主題の提示部になっている。続く練習番号1から練習番号2までの部分では、M1、M2による展開がなされている。練習番号2において新たな動機M3に基づく主題が提示され、練習番号3から練習番号4にかけてM3がトゥッティで繰り返されながら調性は変ロ短調へと移り変わる。練習番号4において拍子は6/8拍子になり、変ロ音上のエオリア旋法的特徴を持つ動機M4、M5からなる新たな主題が提示され、それらは練習番号4から練習番号5にかけてトゥッティで繰り返される。練習番号6から練習番号7の間では更にテューバによってM4、M5が展開される。練習番号7はM4の動機を用いて、変ロ短調からイ短調へ、6/8拍子から2/4拍子への転換が行われる経過句で、練習番号8では更に主調であるヘ短調に転調する。ここではテューバとオーケストラによってM1、M2が展開され、練習番号9ではM2、M3が展開される。練習番号10においても続けてM3による展開が行われ、練習番号11から練習番号12にかけてのオーケストラのトゥッティからテューバのカデンツァへと移行する。カデンツァはM2とM4に基づいている。コーダはM5によるもので、ここではピカルディ終止が使われている。カデンツァでは前述のように2つの高音部でのカットが示唆されているが、これは当時の演奏技術を考慮してオミットされたものである。作曲者の言葉にもあるように、この楽章は全体的にみてバッハの時代の協奏曲のような独奏とトゥッティが交互に現れるコンチェルト・グロッソ的な形式を持っている。また、特徴的な5つの動機が楽章全体に渡ってほぼ均等に用いられており、それがこの楽章の統一感を形成しているといえるだろう。
第2楽章 ロマンツァ アンダンテ・ソステヌート(4分音符=60)ニ長調 3/4拍子。
冒頭から練習番号1にかけて、オーケストラによる前奏が行われた後、テューバによる独奏が現れる。この旋律T1はニ長調であるもののその第7度音が導音的性格を持つことが殆ど無く、練習番号2に入った後のこの旋律の終止部はロ短調になっている。再び歌われる旋律はニ長調であるものの、ト音上のリディア旋法的な和声付けが行われている。第1の復縦線の前で嬰へ音が半音下げられ、ニ短調へと転調する。この復縦線の後にポコ・アジタートの指示がみられる。ここからのオーケストラによる旋律T2は、テューバによって歌われた旋律T1の変奏であり、ニ音上のエオリア旋法的である。これは練習番号3を経過して第2の復縦線で4度下がりイ短調へと転調する。ここでオーケストラからテューバに主導権が引き継がれ、イ音上のエオリア旋法で旋律T2が展開される。この旋律も第3の復縦線で先程と同じく4度下がり、今度はホ短調へと転調する。ここから練習番号5に向けては旋律T2の終結部で、練習番号5において旋律T1がロ音上のエオリア旋法で再現される。調性的にも再現されるのは練習番号6からで、この部分は同時にこの再現部の終結部の役割も担っている。練習番号7~練習番号8は、コーダの役割を持っており、旋律の終結部では再び嬰へ音が半音下げられるが、最終的に和音はニ長調で終わる。全体的にはT1-T2-T1の2部形式であるが、T2の部分がT1の変奏的要素であることが特徴的である。しかしながら、旋法性を多用し、単調さを回避して変化に富む音楽構成を作り出していることは注目されよう。
この楽章に限って、作曲者自身の指示により、チェロやバスーンによっても演奏され得る事が示唆されている。
第3楽章 フィナーレ-ロンド・アラ・テデスカ(ドイツ舞曲風に) アレグロ(4分音符=150) 3/4拍子。
楽章の冒頭に示されている通り、ドイツ舞曲風のロンド形式をとっている。序奏部では F-A-H-C-Des-Es-F という音列TS1、ロンド主題では F-G-As-H-C-Des-Es-F (エオリア旋法の第4度音を半音上げたもの)という音列T2が基本として用いられている。また、4分音符=150(Tem.A)という指示の他に付点2分音符=50(Tem.B)という指示もなされており、これは実質上同じ速さであるものの、随所に見られるポコ・アニマートに対応する指示とみることが出来る。
冒頭から練習番号1までは、序奏部にあたり、TS1が用いられている。譜面は4分の3拍子で書かれているものの、旋律は4分の3+4の7拍子で書かれており、それがオーケストラとテューバの間でカノン的手法で扱われている。序奏部はヘ長調の主音で終わり、続いてTS2を用いてロンドの主題T1が現れる。次にオーケストラのトゥッティに挟まれてTem.Bによって新しい主題T2がオーケストラ→テューバの順で現れる。移行部(序奏部の動機が用いられる)を挟んでT1に戻り、更に新しいテーマT3(Tem.B)が歌われる。これはT2とは逆にテューバ→オーケストラの順に現れる。調的(音列的)には安定しているロンド主題T1に対して、それに挟まれる主題T2、T3は共に変化記号も多く、調的に不安定である。練習番号6ではオーケストラのトゥッティによってT2とT3が同時に奏され、練習番号7での序奏の変奏を経てロンド主題T1に回帰する。T2を用いた経過部がテューバ、続いてオーケストラで奏された後、カデンツァに入る。カデンツァは序奏の動機とT2の動機が用いられ、カデンツァの終了と同時にオーケストラのトゥッティを伴って曲は閉じられる。形式的には次のようにみることが出来る。
| 序奏(Tem. A)-T1 | Tuba→Orch. | 音列の使用 | A |
| T2 (Tem. B) | Orch.→Tuba | 調的に不安定 | B |
| 序奏(Tem. A)-T1 | Tuba | 音列の使用 | C |
| T3 (Tem. B) | Tuba→Orch. | 調的に不安定 | B |
| 序奏(Tem. A)-T1 | Tuba | 音列の使用 | A |
| T2 (Tem. B) | Tuba→Orch.(T2+T3) | 経過句 | B’ |
| 序奏+T2(Cadenza) | Tuba→Orch. | 終結部 | Coda |
以上のように形式的にはA-B-C-B-A-B’-Codaのロンド形式の構造を持つものの、序奏の動機が重要な役割を果たしていることや、経過句における様々なテーマの組み合わせる手法は特徴的であろう。また、
調性とテンポの設定によって作られた安定した主題と不安定な主題の対比、交互に現れるソロとトゥッティのセクションごとの入れ換えによって、この楽章は大変劇的な要素を獲得している。
まとめ
以上の分析のように、この《テューバ協奏曲》は、随所に見られる旋法の使用や、特に第2楽章に見られる和声法の点から、親しみやすい旋法的な旋律、和声の流動的な運動、といった彼の作曲技法上の特徴がよく現れていると結論付けられよう。また、小規模の楽器編成や、特に第1楽章に見られるバロック的協奏曲構成からも、テューバとオーケストラの音量的バランスを少なからず考慮していたことが推察される。
更に、全楽章を通じてのテューバの特徴的音色、性格がよく捉えられた旋律作法と共に、速いパッセージや高音域の連続的使用といったヴィルトゥオーゾ的要素も取り込んでいることから考えても、この曲はテューバの為の協奏曲として非常に完成度の高い曲ということが出来るだろう。
2014年10月26日追記:日本では2013年6月に入手が可能となったOxford版の第二版について、同年6月18日にフェイスブックに投稿したレヴュー1.2.
を転載します。いつか本文にも反映させる予定。
最近話題のRVWの新版、スコアと一緒に頼んだはずなのになぜかリダクションだけ先に届いたので、いそいそと開封。ざっと見比べてみました。
1.浄書がコンピュータソフトによるものになりました。
2.表紙はパート譜のほうについています。
3.練習番号のほかに小節番号がつきました(嬉しい!)
4.パート譜は若干間が広めで読みやすい。所々レイアウトが変わっています。
さて肝心の改訂内容ですが、パート譜のほうにはソロパートの改訂報告がついています。これによると全部で17箇所。主にダイナミクスやアーティキュレーション記号が変更されています。何れも「あ、そうだよね」といった感じのもの。第一楽章のカデンツァは一番最初の版が採用されて、二か所とも最高音がAsまでになりました。
個人的にちょっとびっくりしたのは第二楽章で、ここでは従来のスラーに加えて、オリジナルに書かれているスラーがドットで示されています。これは随分と違う箇所にかかっているので、今後検討や試行錯誤が必要なのでは、といった感じ。全体を通して音の変更はありません。よく問題となる第二楽章の88小節目(練習番号4の8小節目)も変更なしです。これは改訂報告によるといくつかある一次資料で相当に表記に揺れがあるようで、それが原因で混乱しているんですね。
ピアノリダクションについては、そのリダクションの方法はほぼ旧版を踏襲しています。こちらは改訂報告なし。明確に誤植であった音は見た限りすべて訂正されていました。まだ見ていないので判りませんが、スコアで訂正した部分が反映されているようです(ダイナミクス、アーティキュレーション)。(一か所早速誤植っぽい所を見つけたのですが、これは新版のスコアで確認が必要。)
チューバの人、買いですよ!
前回に引き続いてRVWのスコアが到着したので軽いレヴュー。 さて、こちらも訂正箇所について読んでいると中々に面白いです。 1.ある版には第三楽章の84小節から6小節間、トロンボーンのパートがあったらしい。現行版ではどの出版譜でも丸々カットされている(どうも派手すぎてソロに被ると判断されたらしい)。 2.同じくある版では第二楽章のエンディングが違う(RWVの存命中から全く出版譜に反映していないのでボツらしい)。(※これが73小節目の音の変更のことを指しているのかどうかは不明。) 3.リダクション版とも被りますが、第二楽章にはRVWがもともと想定していたフレージング・スラーが破線で記されています。この掲載にはジェームズ・ガーレイの助言があった模様。 ピアノリダクション版にも記載されている部分を省くと、第一楽章12、第二楽章7、第三楽章19、計38箇所についての言及があります。これらについて旧新両方のピアノリダクション、オイレンブルグのポケットスコアと比較してみます。 多くの場合はダイナミクスやアーティキュレーションを他のパートと揃えたり、明らかな音のミスを訂正したり、といった細かいものなのですが、 幾つかの部分で旧版のピアノリダクションからも音が変更されています。 第一楽章第55小節、第二楽章第18小節、第33小節の3か所。 こうして新版のポケットスコアを片手に新旧のピアノリダクションを比べてみると、旧版を下敷きにしながら丁寧に訂正が重ねられていることが見てとれます。特にダイナミクス、アーティキュレーションについては、一つ一つは小さな違いなのですが、それらを重ねていくと少し印象が変わるのではないか、と思います。つくづくこういった仕事には頭が下がります。 (追記)前回のポストで抜けていたので追加。 第一楽章のカデンツァ、Lentoの前の三連符は旧版ではF-Es-Gesですが、これがF-Des-Gesになっています。
参考文献
注) 現在下記の多くの洋書は第2版が出版されている。
| Butterworth, Neil. Ralph Vaughan Williams : A Guide to Research. Garland Publishing, 1990. x, 382p. |
| Catelinet, Philip. “The Truth About the Vaughan Williams Tuba Concerto”. TUBA Journal, Greenboro: Tubists Unibersal Broherhood Association, 1991. pp 52-70. |
| Day, James. The Master Musicians Series : Vaughan Williams. New York: J.M. Dent, London, and Farrar, Straus and Cudahy, 1961. 228p. ISBN 6-106510-6. |
| Dickinson, A. E. F. Vaughan Williams. London: Faber and Faber, 1963. 540 p. ISBN 6-400095-3. |
| Douglas, Roy. Working with Vaughan Williams – The Correspondence of Ralph Vaughan Williams and Roy Douglas. London: The British Library, 1988. viii, 119p. ISBN 0-7123-0148-8. |
| Kennedy, Michael.The Works of Ralph Vaughan Williams. London: Oxford University Press, 1980. 454p. |
| Kennedy, Michael. A Catalogue of the Works of Ralph Vaughan Williams. London: Oxford University Press, 1982. 329p. |
| Schwartz, Elliott S. The Symphonies of Ralph Vaughan Williams. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1964. 242p. Library of Congress catalogue #64-24402. |
| Vaughan Williams, Ursula. R.V.W – A Biography. London: Oxford University Press, 1973. xiv, 448p. ISBN code 0192820826. |
| ラルー,ヤン・大宮真琴 『スタイル・アナリシス 統合的様式分析―方法と範例』1、音楽之友社(1988年)、500頁。 |
| 船山隆「ヴォーン・ウィリアムズ」『音楽大辞典』 平凡社,1981‐83年 第1巻、(1981年)、226頁。 |
使用楽譜
| Vaughan Williams, Ralph. Concerto for Bass Tuba and Orchestra. London: Ernst Eulenberg Ltd.,. 1982. v, 72p. |
| Vaughan Williams, Ralph. Concerto for Bass Tuba and Orchestra, Arrangement for tuba and piano. London: Oxford University Press. 1955. viii, 22p. |
CD
| Vaughan Williams: Symphony No. 5, etc. John Fletcher, soloist; London Symphony Orchestra; Andre Previn.(一口解説:定番。名手ジョン・フレッチャーによるもの。レコーディングは古い時期で、マイクの集音の関係からテューバをオーケストラの中央に置いて録音した、との苦労話もある(噂)。) |
| Symphony 6 / Tuba Concerto. Patrick Harrild, soloist; London Symphony Orchestra; Bryden Thomson.(一口解説:同じく定番。カデンツァは楽譜の指定どおりに行っている。ヴォーン=ウィリアムズのコンチェルトを集めた2枚組のCDはこちら。) |
| “聖なる少年,牧歌~ブリティッシュ・チェロ・アルバム”Julian Lloyd Webber, soloist; ASMF, Neville Marriner.(一口解説:チェロのジュリアン・ロイド・ウェッバーによる第二楽章「ロマンツァ」の録音。歌い回しに楽器の違いが出ている点が興味深い。輸入版はEnglish Idyllsのタイトルでリリース。) |
| Virtuoso Tuba.Michael Lind, soloist; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Leif Segerstam.Caprice, #21493(一口解説:ミカエル・リンのアルバム。上記の演奏に比べるとさらっとクールに纏まった感あり。ヤコブセン、ルンドクヴィストのコンチェルトも聴きごたえあり。) |